

| 1971年 | 群馬県太田市に生まれる 太田市立韮川小学校、太田市立北中学校 卒業群馬県立太田東高校に入学、一年間の米国留学の後 |
|---|---|
| 1989年 | 同校中退、大検取得 |
| 1990年 | 早稲田大学政治経済学部政治学科入学 |
| 1994年 | 同校卒業 |
| 1996年 | 横浜国立大学工学部建設学科海洋工学コース入学 |
| 2000年 | 同校卒業 太田市環境基本計画市民ワーキング部会 会長(~01) 太田市行政改革推進委員会 副委員長(~02) 八ツ場ダムを考える会 会員 太田市広報市民編集委員(~02) |
| 2001年 | 2001参院選群馬選挙区における公開討論会実行委員会事務局長 |
| 2002年 | 子どもを育てるなら群馬県推進会議委員(~06) 群馬県社会教育委員(~06) |
| 2003年 | NPO法人おおたファミリーサポートセンター 理事(~08) 八ッ場ダムを考える市民の会おおた 代表 |
| 2004年 | 太田市水道モニター(~06) |
| 2005年 | 太田市まちづくり基本条例検討委員会 副会長(~06) 太田市NPO法人連絡協議会 会長(~07) |
| 2007年 | 群馬県議会議員選挙 当選 |
| 2011年 | 群馬県議会議員選挙 2期目当選 |
| 2015年 | 群馬県議会議員選挙 3期目当選 |
| 2017年 | 太田市長選立候補 惜敗 |
| 2019年 | 群馬県議会議員選挙 4期目当選 |



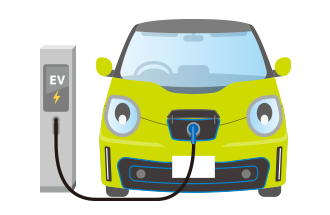

わたしは、初めての子どもが生まれたとき、そのあまりにも無力な存在に、自分自身の責任の重さを感じないではいられませんでした。 わたしの親が、その親が、わたし以外の人たちの多くの親たちやその親たちが、いままでさまざまな困難のもと、人の生きる道を広げる努力を してきてくれた結果、いまわたしはこうして大人になり、有権者となり、社会に対して発言もできるし、働きかけをしていくこともできるように なったのだということを、生まれたばかりの子どもの無力さに出会って改めて実感したのです。
そして、いまは自分の頭を持ち上げることさえできない子どもたちが、大人になって自分たち自身で社会に対し、働きかけができるように なるまでは、親として、大人として、わたしが社会を少しでも住みやすいものにして手渡せるように頑張らなければと思った時、はたして今の自分は、 できるかぎりのことを100%しているといえるのだろうか、と考えざるを得ませんでした。
おなかが大きくなって感じた、足元が見えない下りの階段の危険さ、子どもが生まれて感じた、出産の大変さや経済的な負担の大きさ、 ベビーカーを押しながら気づいた道路の段差や歩道のない道路の多さ、子育てと仕事の両立の難しさ、そういった様々な生活の中にある問題に気づいたなら、 それらを変えるためにもっと努力することができるのではないだろうかと。
初めての県議選へのチャレンジは、上の子が7か月の時、二度目の挑戦は下の子が1歳4か月の時、そして三度目の挑戦で、太田市選挙区初の女性県議として 当選させていただくことができました。
その間、子育て支援のNPOを立ち上げたり、市や県におけるさまざまな公募委員として発言させていただいたり、市内の多くの地域を回って一人一人の 県民の皆さんの声を聞かせていただいたりしてきました。
老親の介護に直面して初めて、すぐに入所できる施設がないことに気付いたという方、ハイリスク妊娠で、市内に産める病院がなく、遠く前橋まで 通っているという方、お孫さんの面倒を見ているけれど、長期の休みの期間に一日中みるのは体力的にも大変で、学童保育で休みの期間だけでも預かって もらえたらと訴える方、世のため人のためと思ってボランティア活動に励み、持ち出しで活動しているのに行政の支援がなかなか充実しないという方、 多くの声を聞くたびに、いまの県民の生活と、政治や行政の距離が離れてしまっているのではないかと思わずにはいられません。
人口も経済も右肩上がりに伸びていた時代から、社会の在り方が大きく変化した今、市民の声を聞くことはさらに大切になっています。 考えられないようなスピードで変化する経済や生活に直面し、必要なタイミングで手立てを講じるには、実際に現場にいる人たちの声を聞くしかありません。 わたしは、この困難な時代を少しでも明るい方向に向けて子どもたちに手渡していけるよう、市民の皆さんとともに取り組んでいく決意です。